- 香川大学DXラボのスタッフブログでは、DX推進の現場で活躍する学生や研究員のリアルな声をお届けしています。今回の記事は、2024年度にDXラボのスクラムマスターとして活動してくれた冨田さんへのインタビューをもとに、彼がどのように現場で成長し、どんな視点や工夫を持って取り組んできたのかを深掘りします。
他の記事ではあまり語られていない「自分なりのリーダーシップのあり方」や「現場での意思決定の難しさ」「学生同士の関係性の築き方」など、冨田さんならではの視点が伝わる内容になっています。
※2025年3月19日インタビュー
※所属や職階は記事公開時点のものとしています。
学生
【DXラボスタッフOBに聞いてみた】たぬきチームスクラムマスター 冨田 邦宏
「全部自分で」から「みんなで一緒に」へ
迷いと成長のスクラムマスター 譚

DX推進研究センター客員研究員 油谷知岐
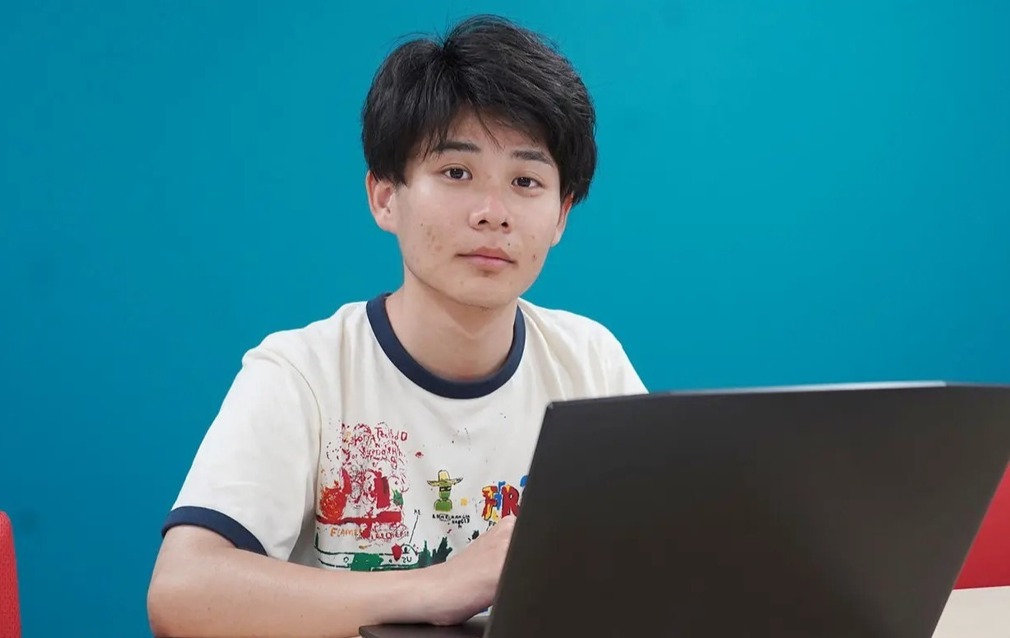
DX推進研究センターDXラボスタッフ卒業生 冨田邦宏

DX推進研究センター特命教授 浅木森浩樹
スタッフが開発したシステムはこちらをご覧ください
※インタビュー内容の一部はMicrosoft Copilotを用いて自動要約し、一部修正を加えたものです
自己紹介
油谷:こんにちは。DX推進研究センター客員研究員の油谷です。
浅木森:同じくDX推進研究センター特命教授の浅木森です。
冨田: 2025年3月に香川大学大学院博士前期課程を修了し、現在は大手電気機器メーカーに勤務している冨田です。 2024年度にDXラボのたぬきチームのスクラムマスターとして活動しておりました。よろしくお願いします。
自分なりのリーダーシップを模索する
油谷:冨田さん、まずは当時のDXラボでのご自身の役割について教えてください。
富田:はい。私は2024年度からスクラムマスターとして、学生チームのまとめ役をしていました。2023年度までは先輩の下で指示を受けながら動いていましたが、2024年度からは自分がチームを引っ張る立場になりました。
浅木森:立場が変わってどんなことを意識するようになりましたか?
冨田:最初は「自分が全部やらなきゃ」と思い込んで、何でも自分で抱え込もうとしていました。でも実際にやってみると、全部自分でやるのは無理だと気づきました。そこでメンバーに仕事を振ったり、相談したりすることの大切さを学びました。
油谷:なるほど。自分で抱え込まずに周りに頼ることもリーダーの大事な役割なんですね。
冨田:そうですね。最初は頼るのが苦手だったんですが、周りのメンバーが「何かあったら言ってね」と声をかけてくれたり、困っているときに自然と助けてくれたりして、少しずつ頼れるようになりました。
浅木森:それは素敵なチームですね。逆にリーダーとして難しかったことはありますか?
冨田:やっぱりタスクの割り振りや進捗管理が難しかったです。どこまで自分が口を出していいのか、どこまで任せていいのか、そのバランスを取るのにずっと悩みました。
油谷:そのあたりは他のチームの同期のスクラムマスターのみなさんとは少し違った観点ですね。
学生同士の関係性と現場の空気づくり
浅木森:DXラボの活動を通じて、学生同士の関係性について感じたことはありますか?
冨田:はい。2023年度までは先輩がリーダーで、僕たちは指示を受けて動く立場でした。でも自分がリーダーになって、後輩たちとどう関わるかをすごく考えるようになりました。
油谷:具体的にはどんなことを意識していましたか?
冨田:例えば、後輩が意見を言いやすい雰囲気を作ることです。自分が一方的に指示を出すのではなく、みんなの意見を聞いて、できるだけフラットな関係で進めるように心がけていました。
浅木森:それは難しそうですね。実際にやってみてうまくいったことや課題はありましたか?
冨田:うまくいったのは、定例ミーティングで「最近どう?」と雑談から始めてみんなが話しやすい空気を作ったことです。逆に課題は、やっぱり自分がリーダーだと、どうしてもみんなが遠慮してしまう場面があることです。
油谷:そのあたりはどうやって乗り越えようとしましたか?
冨田:自分から失敗談を話したり、「わからないことがあったら一緒に考えよう」と声をかけたりしていました。完璧なリーダーじゃなくていいから、みんなと一緒に成長していける雰囲気を大事にしたいと思って活動していました。
現場での意思決定と迷い
油谷:DXラボの活動では、現場での意思決定も求められると思いますが、どんなことを意識していましたか?
冨田:そうですね。例えば、プロジェクトの進め方やタスクの優先順位を決めるとき、最初は自分の考えだけで決めてしまいがちでした。でも実際にやってみると、他のメンバーの意見を聞いたほうがうまくいくことが多いと気づきました。
浅木森:それはどんな場面で感じましたか?
冨田:例えば、ある案件で自分が「こうしたほうがいい」と思って進めていたら、後にメンバーから「こうしたほうが効率的じゃない?」とアドバイスをもらってやってみたら本当にうまくいったことがありました。
油谷:自分の考えに固執せず、柔軟に対応することが大事なんですね。
冨田:はい。最初は自分のやり方に自信がなかったのでつい固執してしまったんですが、今は「まずやってみて違ったら直せばいい」と思えるようになりました。
浅木森:それは大きな成長ですね。
自分なりの成長と今後の目標
油谷:DXラボでの活動を通じて、自分自身が成長したと感じる点はどこですか?
冨田:一番は人前で話すことに慣れてきたことです。最初は緊張してうまく話せなかったんですが、定例ミーティングの司会や発表を重ねるうちに少しずつ自信がついてきました。
浅木森:今後どんな自分になっていきたいですか?
冨田:今はスラクムマスターとして、チーム全体を見ながらサポートする役割を頑張りたいです。将来的には、他のメンバーが困ったときに頼られる存在になりたいですし、自分自身ももっと技術力を高めて、いろんな分野にチャレンジしていきたいと思っています。
油谷:素晴らしい目標ですね。応援しています。
現場での学びを社会にどう活かすか
油谷: 最後に、DXラボでの経験を今後社会にどう活かしていきたいですか?
冨田:DXラボで学んだ「自分だけで抱え込まず、周りと協力して進めること」や「失敗を恐れずにまずやってみること」は、どんな職場でも大事だと思います。将来はこうした経験を活かして、どんな現場でも柔軟に対応できる人になりたいです。
浅木森:ありがとうございます。冨田さんの経験は、これからDXラボに参加する人や他大学でDX推進に取り組む方にもきっと参考になると思います。
冨田:ありがとうございます。僕自身もこれからもいろんなことにチャレンジしていきたいです。
おわりに
今回のインタビューでは、2024年度にDXラボのスクラムマスターとして現場をまとめてくれた冨田さんの「自分なりのリーダーシップの模索」や「学生同士の関係性づくり」「現場での意思決定の難しさ」など、他の記事ではあまり語られていないリアルな悩みや成長の軌跡をお伝えしました。
香川大学DXラボの現場で得られる学びは、きっと他の大学や組織でも活かせるはずです。今後もスタッフ一人ひとりのリアルな声をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。

